また、、浅井郡三河出生、比叡山中興の祖、第18代天台座主、元三慈恵大師良源大僧正(912-966)が、当寺にたびたび参籠休息したと伝えられています。しかし、元和3年8月(1618)後陽成院の崩御のため、涅槃宗への心ないものの讒言がおこり、本山涅槃寺は破却されることとなりました。時は徳川幕府による宗教統制の時代でした。
このとき、慈眼大師天海大僧正が後陽成院の遺託と及意上人の依頼により、直筆の寺号額を当寺に与えました。また、第三祖を自らの弟子とされ、念海上人との法号を授け当寺住職として、その破却から当寺を守られたのです。
また天海大僧正は、当寺をたびたび訪れ、境内に及意上人がこよなく愛された松をお植えになり、上人の御遺徳を偲ばれました。これらの縁により、当寺は日光輪王寺門跡直末となりました。その後山門滋賀院門跡直末等へ経て現在に至っています。
現在の本堂は、寛政年間(1790)に大火にあい焼失、文化3年(1806)輪王寺宮公澄親王の命により、延暦寺僧網職にあった当山20代住職義空和尚が、檀徒と一丸となり十数年の歳月をかけ再建されたものです。


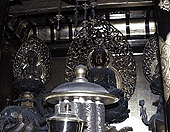 釈迦三尊像
釈迦三尊像




地蔵堂 長浜市指定文化財